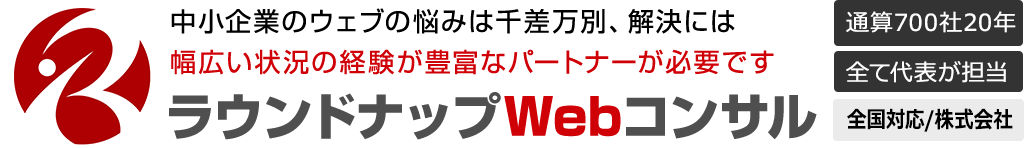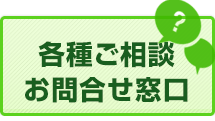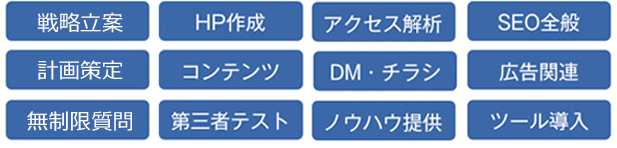おはようございます、ラウンドナップ中山です。溜まっていた某経済誌を一気に目を通したのですが、「ポストコロナの顧客戦略」という特集の中で、ちょっと怖いなという内容がありましたので、それに対するコメントと、中小企業の方に気をつけていただきたい点を今回はお届けできればと思います。
具体的には、以下のような内容です。このような論旨は該当記事に限らず、よくあります。
- 日本企業はブランド戦略が未だに弱く、場当たり的である
- 先進的な海外企業(J&Jやコカ・コーラなどがよく挙げられる)はブランド資産を構築している。そのため新規事業への拡張などがしやすい
- 日本企業もきちんと中長期を見たブランド戦略をたてなければいけない。
- その差異起点になるものの一つが「創業時の精神」だ、なぜなら多くの日本企業では創業時精神に強烈な想いやこだわりがあるからだ。それを使わない手はない。
- それを今に合わせて伝わるようにアレンジしてみると良い
ただ、これは行間に注釈を色々入れていかないと、誤解を招く怖い論旨です。
一歩間違えると
「独りよがりで、今の時代に通じないブランド戦略」
をとってしまう可能性があるからです
なぜでしょうか?今回はそれがテーマです。
目次
今回のテーマ
- 創業時と今とではお客さんの価値観が大きく異なる
- 「原点回帰」という分かりやすい言葉に惑わされてはいけない
- 創業時の精神は役に立たないかというと、そうではない
- 無理やり形だけのものを作ることのリスク
- 場合によってはゼロベースで考えたほうが良いです
- 今週のWebセミナー / Podcast
- ブログ更新を再開しました
- LINE@まとめ
- あとがき
今週のトピックス
おはようございます、ラウンドナップの中山です。
創業時と今とではお客さんの価値観が大きく異なる
まずそもそも、日本企業は歴史の長い企業が多いです。100年企業という言葉があります。文字通り創業から100年を超えている企業ですね。この100年企業のうち日本企業はどれくらいあると思いますか?
帝国データバンク、ビューロー・ヴァン・ダイク社のorbisの企業情報(2019年10月調査)によると、全体の41.3%が日本です。半分近いんですね。
全体的に、日本は長年やってきた企業が多いのです。
仮に半分の50年だとしても、創業時と今、事業環境はもちろんお客さんの考え方や価値観も大きく変わっています。
創業者の精神はその時の社会環境に対しての「なんとかしなければ」といった思いが占める部分が大きいですから、それが周りに響くかどうかはその時代背景に大きく影響されるのは明らかです。
すなわち、創業時の精神をそのまま持ってきても、響かない可能性のほうが大きいのです。
「原点回帰」という分かりやすい言葉に惑わされてはいけない
日本人は「原点回帰」という言葉が好きなように思います。それは恐らく、様々な文明を自分のものとして柔軟に取り込んできた歴史の一つの裏返しではないかと思います。
そしてこの「創業時の精神に立ち返る」というのも、まさに原点回帰の典型例です。なので、なんとなく納得してしまうのだと考えます。
しかし、実際「そのまま創業時の精神を持っててきてブランド価値の中有心にすえてうまくいく例は極めて少ない」と考えたほうが良いです。
理由はシンプルで、そのまま持ってきても、時代に合わないからです。今の人に響かないからです。ひとりよがりになってしまいがちだからです。
創業時の精神は役に立たないかというと、そうではない
では、創業時の精神などは意味がないかというと、決してそうではありません。大事なのは、時代性を剥ぎ取った上で残る「コア」を見つけて、それを今の時代に合わせて表現できれば、今の時代に通じるストーリーやコンセプトに消化できる可能性があります。
時代性を剥ぎ取ると、シンプルに社会をどうしたかったのかが見えてきます。
「何かを民主化したかったのか(上の方の人しか手に入らないものを、あまねく手に入るようにしたかったのか)」
「解決されていない課題を、何かの手段で解決する挑戦をしたかったのか」
「タブーを破って、透明性の高い何かを作りたかった」
などなど、その会社の成り立ちとしての性格が見えてきます。
それをむき出しにした後に、今の社会の中でどうそれを表現するか考え、コンセプトとして落とし込む。それを納得してもらいやすくするために、創業時の精神をストーリーとして使う。この形なら使えるものになります。
この流れであれば、うまく使えるはずです。私もコンセプト構築の中で、この「時代性剥ぎ取り」と「今への落とし込み」は必ず頭の中で行っています。
無理やり形だけのものを作ることのリスク
そして、時代性を剥ぎ取ったとき、ブランドやストーリーとして使えるものがないケースもあります。端的に言えば「会社を大きくしたかったから」「食うためにやった」ようなケースです。特に戦後初の企業に多いです。
これは悪いことではないです。当然のことです。そして、そういう企業の方が多いのではないでしょうか?
私がおすすめできないのは、こういう会社なのに、何か色々お化粧をしたり無理やりストーリーをこじつけて、さも昔から理念が合ったかのように装うことです。
なぜおすすめできないか?
それは一言で言えば「バレる」からです。お客様からも、そして社内からも。
HPリニューアルのご相談を頂いた場合、私はコンセプトの把握から入ります。
その際、いろいろな方にご意見を伺う機会があります。そうすると少なくない割合で「今のホームページのキャッチや打ち出しには納得していない」というご意見を聞くんです。「売るためにそうしてるんですよね(実際現場で考えたこともないですが)」という声です。
こういう状態の場合、お客さんにも響きませんし、社内でそのコンセプトに沿って一貫性のある行動が取れるわけがないので、反響が取れてもその後の成約やリピート率がなかなかあがりません。
場合によってはゼロベースで考えたほうが良い
無理やり作った「強み」や「物語」や「理念」はむしろマイナス要因になります。
その場合は、もうゼロベースで「今私達は何をしたいのか」を考えて、それを使うことをお勧めします。従業員の方も巻き込んで、まず社内で納得できるものを作っていきませんか?
そのほうが社内の足並みも揃いますし、お客様にも響くものができます。無理やり海外の事例に当てはめて、創業時精神なんて持ち出すとおかしくなります。
ぜひ、無理矢理ではなく今のみんなで作り上げる、そんな形で差別化のためのコンセプトを作り上げてみてはいかがでしょうか。
Webinar最新回のご案内
第288回:Googleマップの機能追加から見える、中小企業が早めに着手すべきこととは?
今回は、5月18日に開催された開発者会議「Google I/O」で発表されたGoogleマップへの機能強化について。
具体的には「ライブビュー簡単利用」「混雑状況マップの提供」「急ブレーキを踏む内で済むルートを提案可能に」「より精細で現実に近い地図」そして、ユーザーの時間帯や状況に応じて表示する内容を変えるパーソナライズなどの機能について、
それが実装された先の未来についてと、それまでに準備しなければならない内容をお届けしています。
Get around and explore with 5 new Google Maps updates
https://blog.google/products/maps/five-maps-updates-io-2021/
配信はこちらから
YouTubeのみ動画です。バックグラウンド再生でどうぞ。
iTunes公式ディレクトリPodcast音声配信
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
GooglePodcast
http://bit.ly/google-podcast-jp
Spotify
https://open.spotify.com/show/0yBHyUelJHFtby5uD06UxU?si=fL7RT_T9RPivEu7cAjhqFA
YouTube
https://youtu.be/uspZ0t9NN5g
ほか「中山陽平 podcast」などで検索ください。
ブログでのテキストコンテンツ配信をはじめました
テキストコンテンツの配信を再開しました。新ためてうちのマーケの仕組みを見るとフロントが弱くなっていたため、強化します。既存のWebセミナーの内容を土台に、アップグレードしてほぼ描き下ろしています。ぜひどうぞ
- 中小企業の実践動画コンテンツ活用法とオススメの「最初の一歩」
https://roundup-inc.co.jp/small-biz-howto-use-movie/ - B2Bホームページの活用の第一歩は、自社営業プロセスの可視化から
https://roundup-inc.co.jp/b2b-hp-katsuyou-firststep/
お役に立てましたらSNSなどでシェアいただければ嬉しいです。
LINE@再開しました、ピックアップです
平日ほぼ日刊で、400文字に収まる範囲でニュースへの雑感をお送りしています。ぜひ。
登録はこちら → https://lin.ee/5NzoMnY
その中から最近のものをいくつか抜粋です。いいなと思ったら、ぜひ登録して頂きタイムリーにお受け取り下さい。過去のものも多分タイムラインから見られるのではと…。
[1] バルミューダはスマホの夢を見るか
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2105/13/news111.html
家電製品では一定のポジションを獲得しているバルミューダが、なんとスマホに参入とのことです。同社の発表資料を見ると「コモディティ化したところに、驚きを」という方向性のようです。自社で向上はないので、京セラに委託とのこと。
どう思われますか?私はなかなか厳しいように思います。あるとすれば、光岡自動車的な中身は他社だけど側を思いっきりいじってくる系にして少数生産することでしょうか。
スマホのように体に馴染むものは、操作性に悪い意味での驚きはあってはいけません。使いづらさに直結するからです。使いやすいそしてこんなことも!という形でないとだめなのです。
スマホはOSの縛りもあります。インテリアと家電の間の子でポジションを取ってきた同社が、どういう打ち手を打ってくるのか。これは非常に興味深いと思うところです。
[2] 様々なC向け機能で生活とつながっているLINEの強さにMSがどう戦うのか?
https://www.excite.co.jp/news/article/Cobs\_2239054/
「Teams」個人向け機能の正式提供開始。1対1の通話は24時間無料、グループ通話は60分無料。
まだまだ勝負つかないですね。Teamsの場合機能的には日本だとLINE&BANDとぶつかるのでしょう。様々なC向け機能で生活とつながっているLINEの強さにMSがどう戦うのか?
正直、日本ではMS厳しそうに思います。ビジネスではTeamsは強いです。ただそれがマイナスに働くのではと。
基本、仕事とプライベートを分ける傾向がありますね日本は。で、MSってもうビジネスイメージの塊です。
プライベートの時間ではMS見たくないと思うんですよ。Teams使わないような気がするんですよね。なので、個人向けは見せ方を変えて別のツールにしないと厳しいのかなと。
B向けC向け両方の商品を扱っている方は、分けるべきか、セットで見せるかは大きなポイントになります。ダスキンはセットでうまく行ってますね。
[3] Google、目の前に相手が実在するかのような「Project Starline」発表
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2105/19/news084.html
これは動画を見て「おおぅ」と声が出ました。ぜひリンク先にあるTwitter動画をご覧ください。
本当にそこにいるかのようです。
まだ特別なスクリーンが必要で実験段階ですが、ビデオ会議の行き着く1つの姿がここにあります。
そしてこうなると、もはや人間の目には対面と変わらないでしょう。モニタの解像度が上がって紙と同様の滑らかさが実現されたように、見分けのつかない時代となります。触覚が伝わらないので遠隔診療などにはまだ限界はありますので次はそこですね。
コレが民主化すると、Webでの営業活動も大きく変わりますね。視覚聴覚の範囲ではどこでも移動不要になります。どこでもドアです。なのでデータではなく物体を運ぶ必要があるなら、それは大きな弱点となるでしょう。今でもその流れはあります。
この前提で考えると、どうすればいいでしょうか?
今から準備して備える価値は十分にあります。
[4]コロナ禍の中、進むのは言ってみれば「食事のEC化」
https://japan.cnet.com/article/35170961/
ゴーストキッチンはTVでも取り扱われるなど、聞いたことがある方も多いのではと思います。デリバリー専門店なので、店舗接客がいらない。
なので例えば飲食店なんて入っていなさそうな雑居ビルが、実は中はデリバリー専門店のオフィスと調理場だらけ、みたいな話ですね。
これは、コロナ禍が落ち着いても残るでしょう。スーパーに行かずECサイトで通販して済ますことの便利さと、外食せずにデリバリーで済ますことは、頭の中の回路としては同じです。もともと日本は出前文化がありますし。
こういう言い方もあれですがコロナ禍は「バブル」でしょう。しかしここで資産をためたところが、今後も攻勢に出ていくでしょう。
店舗型は雰囲気や接客を軸にして料理に付加価値をつける路線になるでしょう。
ゴーストキッチンは求める立地・人材・ノウハウ・システムなど異なります。関わる方は情報のチェックをお勧めします。
書籍は最初の一歩にお勧めです
Amazonか大手書店で販売中です。
さて、この本は、企業のウェブ担当者・経営者などの方に伝えたい内容がメインです。
フリーランスでマーケターとしての腕を上げたい、SEOや広告のテクニックを学びたいという方向けの本ではありません。
Amazonだと中身が見られないので、そこだけ気にして頂けると、ミスマッチも少なくなるかなと思います。是非読まれた方はブログやAmazonなどでレビュー書いて頂ければ幸いです。
今後の配信コンテンツの方向性を決める上で、是非生の声を頂きたいです。
今すぐAmazonでご購入ください → http://amzn.asia/15AeH9k
終わりに
今、うちは電話窓口をカットしています。なので基本的には電話はかかってこないはずなのですが…(お客様とはビデオ会議なので)しかし一日10件以上の営業電話が来ます。携帯の番号から050番号、一般回線などさまざまです。
検索して営業電話だと分かった場合着信拒否にしています。メールも相変わらず問い合わせフォームから含めて1日5件以上来ます。FAXは詐欺っぽいの含めて知らないところからのものが週に4−5枚は来ます。
厳しい状況なのだろうというのは分かるのですが、どの会社もやることだらけで余裕のないコロナ禍の中で、そんな営業してどうするんだろうと思うところです。
インバウンドで自然と問い合わせが来るような仕組みづくりが必要ですよね。こういうときこそ、お互いに気持の良い取り引きができるような方向を模索しなければいけないと、日々人の振り見て我が振り直せと思っております。
お困りの方、よろしければご相談ください。
では、また次回もメールしますね。