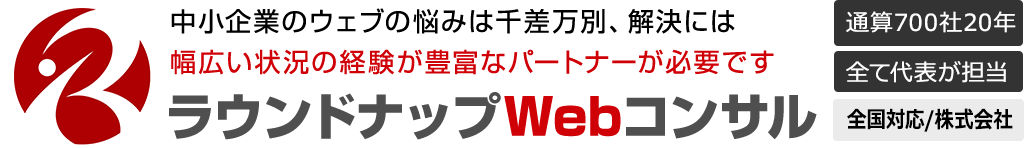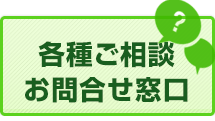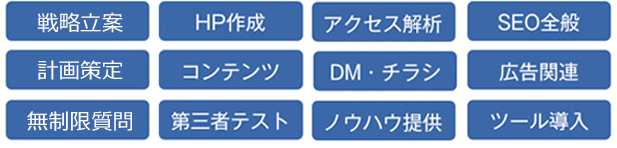目次
今週のトピックス
こんばんは、中小企業のWeb活用パートナー、ラウンドナップWebコンサルティングの中山です。
会社への営業電話がすさまじいです、土日も凄いですね、月曜日の朝に着信履歴を見ると20件くらいあります。
コロナが収束しつつあるところで、需要増加を見越して売り込もうとしているのか、あるいは売り逃がした商材を慌てて裁こうとしているのか、どちらかですね。
どちらかというと厄介なのは後者で
- 「元の販売価格の50%以上の値下げ」
- 「今年限定」
- 「オミクロン株のことを説得材料に使っている」
このあたりが重なったものは、いったん疑った方が良いと思います。
もちろん、良い物もあるので、なんでもNGというわけではないです。ただ、お客さまの代理対応していると、危険性高いなと感じるのは事実。
LINEでも紹介しましたが、Googleのこのコンテンツは、研修資料としてもとても良いと思います。
Grow with Google はじめてのメディアリテラシー – 情報と向き合うとき、子どもも大人もすべきこと – – YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLkq-mu9c_kaUQc6xJ3RC25KeWl32Q3Pf
ありがたいことですね。
と、前段はさておき、今回はGoogleのアップデートについての話題です。
ちょっとSEO強めの内容になりますが、押さえて頂きたいです。
コアアップデートが11月に出ましたが、その話題ではありません。思ったより変化がなかったからです。
それより、少し遅れて発表されたプロダクトレビューアップデート。
こちらの方が、Googleが求める方向性が分かりやすいです。
今年4月にも行われましたので今年2回目。
ちなみにプロダクトレビューアップデートは英語コンテンツでしか対象にされていません。日本語コンテンツには現状影響は無いので、ご注意下さい。
ただ、グローバル展開するのは時間の問題でしょう。英語圏だけで終えるというわけがありません。
商品販売していないから関係ない…訳ではない
プロダクトレビューアップデートについて、商品販売系サイトだけに影響して、他のサイトは関係ないと思っていると、落とし穴を避けられないかもしれません。
恐らく最初に商品レビュー、端的に言えばアフィリエイト畏敬の比較サイト(海外にもたくさんある)が選ばれたのは、rel=”sponsored” と rel=“ugc” の導入のせいでしょう。
結果として、自らあるいはスポンサーのための記事なのか、そうではないのか、情報がたくさん得られたはずです。
そして機械学習データを基に、Googleはこのアルゴリズムを、アフィリエイトや比較サイト以外の拾いコンテンツに広げていくと考えるのは自然。
なぜなら、検索行為の中で多くを占め、そして金銭が動くという意味で人生に関わる重要な物である「購買活動」は、基本的には比較を伴う物だから。
なので、販売を行うサイトは、プロダクトレビューアップデートによってGoogleが何をしたいのかについて、追いかける必要があるのです。
では、何に気をつければ良いのか?
まず、こういう場合はGoogle公式ドキュメントがないか探してみるのがよいです。
実際、合わせて公開された物がこれです。
Write high quality product reviews | Google Search Central
https://developers.google.com/search/docs/advanced/ecommerce/write-high-quality-product-reviews
英語しかありませんが、Google翻訳でぜひ。
12項目並んでいます。簡単に訳します。
- ユーザーの視点で製品を評価すること。
- 製品に関する知識が豊富であることをキチンと示す。
- 製品を使用した際の映像、音声、その他のリンクなどの証拠を提示することで、専門知識を裏付け、レビューの信憑性を高める。
- 製品の様々な性能を定量的に示す。
- 競合製品との違いを説明する。
- 比較検討すべき製品を取り上げたり、特定の用途や状況に最適な製品を説明したりする。
- 独自の調査に基づいて、特定の製品の利点と欠点を説明することができる。
- 製品が前モデルやリリースからどのように進化してきたか、改善点や問題点を説明し、購入の意思決定に役立てることができる。
- その商品のカテゴリーにおける重要な意思決定要素を特定し、その分野における商品の性能を評価する(例えば、自動車のレビューでは、燃費、安全性、操作性が重要な意思決定要素であると判断し、それらの分野における性能を評価する)。
- 製品の設計上の重要な選択と、メーカーが言う以上のユーザーへの影響を記述する。
- 判断材料として他の有用な情報源(自分のサイトや他のサイト)へのリンクを掲載する。
- 読者が希望する販売者から購入できるように、複数の販売者へのリンクを検討する。
考え方としては「自分が使いたい比較サイト」を想定するのが良いと思います。
細かく見るとこの辺の言葉が大事でしょう
「映像、音声、その他のリンクなどの証拠」「性能を定量的に」「の製品の利点と欠点」「重要な意思決定要素を特定」「他の有用な情報源」「複数の販売者」
要するに
「自分に都合の良いことばかり書くな」
です。
一般的なHPでよく見るコンテンツにもいずれこの基準が
これって、比較サイトはもちろんそうなのですが(これが日本に来たら多くの比較サイトや、自分の経験だけを元にしたブログは死ぬと思いますが)
それより、販売系ホームページで作る「私たちの強み」や「他の商品との違い」や「●●の作り方比較(●●には自社の属する商品カテゴリが入る、例えば野菜ですとか、システムですとか、ホームページですとか」といったコンテンツにも、Googleは同じ目を向けてくると思うんですね。
そう考えると非常に悩ましいなと思います。
基本的に、自社のそういったコンテンツって、自分たちのサービスを選んでもらう為に書いているからです。
で、それが悪いかというと、恣意的な物もたくさんあるので、ダメな物はダメと思いますが、とは言え難しい部分もありますよね。
人間って
「良い物だから買う」じゃなくて「良い物だと(思えるから)買う」
じゃないですか。
そんなに自分が持つべき判断基準や、それに基づいた比較情報を元にして判断しないですよね。
また、この方向性が進めば進むほど、どのホームページの比較コンテンツも、どんどん内容が収束していきます。
言いかえると、平たい同じような物になっていきます。それでいいのかな?と。購買ってそういう物なのかな?と。
…
と、疑問はあるわけです。
なので、私はここの動きにはとても注目しています。
これからの売り方に非常に大きく影響すると考えるからです。
ちょっと話が逸れましたので戻します。
「比べる」に対してGoogleがどう捉えているか?
もちろん、プロダクトレビューの考え方を、そのまま一般サービスなどの強み弱みみたいなコンテンツに適用するかというと、しないとは思います。
ただ、皆さんに押さえて頂きたいのは、Googleが「比べる」という行為に対してどのような目で見ていくか、という点が重要だということ。
それに備えて、自分たちの商品やサービスの優位性を示すコンテンツが、
- 根拠の明示されていない押しつけであったり
- お客さんが持っている判断基準を無視していたり
- 優位点ばかりで、本当は存在する劣った点を隠していないか
などはチェックをお勧めします。
※Googleアップデートの有無にかかわらず、お客さんも疑ってみてくるのが当たり前なので、むしろネガティブ要因も先出しした方が良いです。また、強みとして押し出していることが客観的事実として正しいかどうかも、示した方が反応は良いです。
是非このメールをきっかけとして、自社のHPを見直して頂くと良いかなと思います。
だからといって、怪しいNo1サービスや格付けサービスなどは使わないように…。
Webinar最新回のご案内
第308回:みずほ銀行への行政処分ニュースから中小企業が受け取るべきもの- 中小企業を強くする 実践Web活用ポッドキャスト
今回は、ニュースでも大きく取り上げられております、金融庁によるみずほ銀行及びみずほファイナンシャルグループに対する行政処分の話を取り上げます。
これに関して、中小企業の方は、「これは大企業案件かつWebやITに関しての専門家同士の問題で、自分たちとは違う世界のものだな」と思われるかもしれません。
しかし実際には、金融庁の報道発表資料から見えるものからは、たくさんのノウハウや落とし穴を見つけることができます。ぜひその観点で見ていただきたいですし、今回のPodcastも聞いていただければ幸いです。
みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について:金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20211126/20211126.html
□配信スタンド
iTunes公式:http://bit.ly/roundup-podcasts
GooglePodcast:http://bit.ly/google-podcast-jp
YouTube音声のみ配信:https://www.youtube.com/watch?v=fD7s8bsnTfo
LINE@再開しました、ピックアップです
LINE@情報配信再開しています 登録はこちら → https://lin.ee/5NzoMnY
【1】仮想オフィスや没入型ワークスペースへの期待が高まる─ガートナーの国内UXハイプサイクル
https://it.impress.co.jp/articles/-/22373
ハイプサイクルってなんぞや?と思われるかもしれませんが、ガートナーが勝手に作った言葉なんで気にしなくて大丈夫です。一言でいえば、何どれだけ社会に溶け込んだか、みたいなものです。
この記事の図は、リモートワーク周りの技術と思ってもいいかもしれません(本当はVR等なので違うものもありますが)
お伝えしたいのはこの図で、世の中に浸透する際には大概のものが「黎明期」→「過度な期待ピーク」→「幻滅期」→「啓発期」→「安定期」というステップを踏むということ。
コロナの中で、必要に迫られて、恐らく過度な期待と幻滅期の両方を一緒に走ってきたのが日本だと思います。で、最近「また出社に戻った」という話を聞きますが、いま必要性が落ちたので幻滅期が強く出ているのだと思うんです。
で、これから企業がやるべきはフラットな目線で、美味しいところどりをできるかどうかですよね。つまり啓発期に踏み込めるか。非常に大事な時期かと思います。
【2】マーケターがGoogleのローカルSEOの変化にどのように適応すべきか(英語)
https://searchengineland.com/how-marketers-can-adapt-to-googles-local-seo-changes-376371
英語ですが、あんまり日本でまっとうなローカルSEOの記事はないので(だいたいサービスのPR)海外ブログから紹介です。Google翻訳も進化してるのでぜひと思います。
要点としては
- Googleはローカル情報に力を入れている
- 特にレビューについていろいろ試している(レビュー内容大事)
- 外部の情報も重要視している(エゴサ重要)
特にレビュー。数と星の平均値だけなんとかすればいい時代ではないです。今、トピックスみたいな表示でますよね?つまりは内容を見ている。自然言語解析して、ネガポジや顧客感情を判断しようとしています。きちんと書いてくれるお客さんを増やさないと。
そして外部のデータも様々な判断材料にしている模様です。誤解などが広がらないようにエゴサ必要です。デジタルだろうが生々しいお付き合いが大事ということですね。
【3】サンワ、PC/スマホでも操作できる電動式の昇降対応デスク
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2111/30/news153.html
昇降式デスクは、(私のように)座りっぱなしになりやすい人には、お勧めです。ただ、最初は立っているとかなり辛いです。動いていればまだしも、同じ場所でというのが辛いのかもしれません。ピキピキになります、足が。
さておき、集中力が全然違うのと、立ちで始めると私は一気にモチベが湧くのでよいです。記事は電動式ですが、手回し式の手動式なら、この半額以下で買えます。ハンドル回す奴と、足で踏んで天板を腕で上下させる奴がありますが、上に物が多い・重い場合はハンドルがよいです。
結構その日によって、しっくりくる高さが変わりますので、微調整できる奴が良いと思います。私は電動だと気づかずケーブルを挟んだりしてしまうので、手回し式使っています。処分も比較的楽ですし。
そして、合わせて青竹踏みお勧めです。足から来るエネルギー大事ですね。
【4】When Google’s title change goes wrong
Googleが検索結果のタイトルタグを結構変えています。「えっ?」と思われた方は、一度いくつか自分のページがでるキーワードで検索してみてください。以前よりは減りましたが、結構素っ頓狂なものになっていることもあります。
残念ながら、いつどのように変わったのかをある程度直接的に調べるには、公式ではなくサードパーティツールが必要です(私はAhrefsをずっと使っています)本格的にSEOやる場合はどうしても何らかの有料ツールは必要ですね…。
それで変わった日付がわかれば、後はサーチコンソールでCTR比較して影響度を調べることができます。で、大体の場合CTRが悪化するんですね、Googleの生成したタイトルは。ではどうしたら戻せるかというと、決定的なものはなく、結局タイトルを変更してクローラを呼んでの繰り返しかなと思います。
順位落ちてないのに、急に流入が減ったという方は、改めてこのあたり洗えるようにしておくことをお勧めします。
LINE公式アカウントでもトピックス配信しています。裏のような扱いです。メルマガでピックアップするもの以外は、タイムラインにも出さない様になるかと思います。
よろしければLINE公式アカウント登録はこちら → https://lin.ee/5NzoMnY
書籍は最初の一歩にお勧めです
Amazonか大手書店で販売中です。
さて、この本は、企業のウェブ担当者・経営者などの方に伝えたい内容がメインです。
フリーランスでマーケターとしての腕を上げたい、SEOや広告のテクニックを学びたいという方向けの本ではありません。
Amazonだと中身が見られないので、そこだけ気にして頂けると、ミスマッチも少なくなるかなと思います。是非読まれた方はブログやAmazonなどでレビュー書いて頂ければ幸いです。
今後の配信コンテンツの方向性を決める上で、是非生の声を頂きたいです。
今すぐAmazonでご購入ください → http://amzn.asia/15AeH9k
終わりに
乾燥しているせいか、火事のニュースが絶えず、見ていて辛い物があります。TV側の注意喚起という側面もあるのかなと思います。
これが、辛い環境の中で起こった事故や事件でないことを祈るばかりです。コロナはオミクロンも症状の深刻度は低そうで、これから回復基調に行くと思いますが、そうすると、自分と周りを比較して色々考えてしまう人が、増えてくると思うんですよね。
今までは緊急事態だったので、あまり考えなくて良かったのが、ふと我に返ってみるとこんなことになっているのかと。
隠れ倒産も増えていけばなおさら、また、ボーナスの話など出てくるとどうしても比べてしまう人も多いでしょう。(私は経営者なことと役員賞与設定しないマイルールなこともあり、ボーナスはないですが…何となく気まずいですよこの時期)
なるべく分断を起こすような内容を冬の切なくなる時期には、マスコミの皆さんは控えてもらいたいなと思うところです。
来年は、誰にとっても明るい年になることを祈ります。
では、またメールしますね。