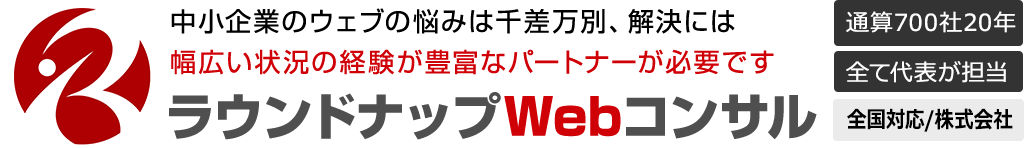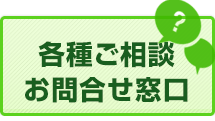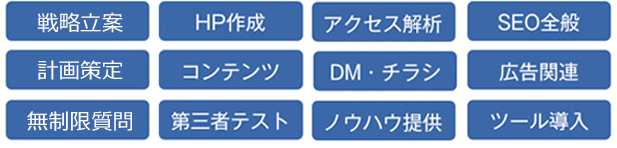目次
こんにちは、ラウンドナップ中山です。
若干緩和しつつも、緊急事態宣言の延長がほぼ決まったようです。
様々な気持ちはありますが、やれることをやる、そして「
※
Webのことだけやっていて、成果を出せる時代ではないです。
さておき本題です。
- 「やれることをやる」の限界、やれることを「作る」ことが必要
- 重い腰を上げざるをえなくなった卸業界から学ぶこと
- 一歩間違えれば自爆するラインを走らざるをえない食品卸
- 今やらないと、始まらない
- 今週のWebセミナー / Podcast
- 対談コンテンツのご案内
- LINE@まとめ
- あとがき
今週のトピックス
おはようございます、ラウンドナップの中山です。
「やれることをやる」の限界、やれることを「作る」ことが必要
この1年で、例えばECを始めるですとか、非対面接客を導入するですとか、いろいろな「やれることをやる」ことをしてきた…という方も多いのではないでしょうか。
しかし、その効果も他に同じことをやる競合他社が増えてくれば、結局優位性はなくなってしまいます。そしてその先には「それが当たり前」の世界が待っています。
そうなると、発想のステップアップが必要になります。
それは「やれることをやる」から「やれることを作る」です。
顕在的なものを網羅するところから、潜在的なものを探って生み出すのです。
最初は自社のもっている既存資産の中から、ニーズがありそうなものを生み出す。
その次は、ニーズをベースに、自分たちでそれを実現できる資産を構築する。
資産は、人的資産、不動産、仕組みという資産、ノウハウという資産など、サービスや製品を世に出すために必要なものです。
これを相当本気でやらないと、同じような自体が数年数十年に一度またやってくる、これからのグローバル世界では、安定した経営ができません。
重い腰を上げざるをえなくなった卸業界から学ぶこと
日経MJの5月7日号に、以下の記事がありました。ネットなので会員でしか読めませんが、一応リンクは張っておきます。
食品卸、直販で内食つかむ: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO71595310W1A500C2H50A00/
ざっくりとは、
- そもそも卸の扱い高はどんどん落ちている(直販、直仕入れ増加)
- 新型コロナで業務用需要が激減して、食品卸が非常に厳しい
- 巣篭もりで好調なB2Cに手を出し始めている
- ただ、金額的にはまだまだ小粒、これから伸ばさないといけない
と言った内容です。実際コロナになる前から卸を通さない買付は増えており、食品中心に卸はその存在意義を問われていました。
また、ただ商品を出せばなんとなく売れた時代でもないので、自社のブランディングなども行いながら直販を中心に行う生産者が増えてきているという流れもあります。D2Cなどもその流れの一つですよね。
それを見ながら、それでもなかなか動かなかったのが、記事にある食品卸だったわけですが、この新型コロナで、そうも言っていられず、新たな販路拡大に取り組んだという流れです。
そんな腰の思い業界でさえ、動かざるを得ないのが今の状況なのです。
そして、未だに成功事例としてあげられている「豊洲市場どっとこむ」でさえ、まだまだ小さな流れという感触だそうです。
この重大性は、改めて感じる必要がありますよね。
一歩間違えれば自爆するラインを走らざるをえない食品卸
今、とりあえずなんとか生き残れているから、このまま行こうと思っている企業様は、危機感を持っていただくことをおすすめします。
先程の卸なんて、実は一歩舵取りを間違えれば自爆する可能性もあることをやっているわけです。
どういうことか?
卸は単純にわければ「直販以外のルートで、生産者と買い手をつなげる」ことに価値があります。
なので、直販頑張っているところも、「卸でしかたどり着けないルートもあるから」ということで、卸も続けるわけです。
逆に新興ブランドなどは最初から直販のみでブランド形成をしていき、それで回るビジネスモデルで回しています。
なので、卸にとっては「生産者自身が直接お客さんとつながる」のはマイナスです。
しかし、こうやってB2Cとして消費者に売るとしたら、様々な付加価値や情報、ストーリーを付けてあげないと売れません。
※記事の中では、ミールキットの開発や、安定して高品質な野菜の頒布会などが挙げられています。豊洲市場&株式会社食文化、スターゼン社、デリカフーズHD社など。
このシステムが成立するのは、「卸がいないと自分たちでは付加価値が作れない、という生産者がたくさんいる」という前提条件があります。
卸側は、生産者をそこに押し込めることに力を入れると思います。
ただ、長い目で見るとどうでしょうか。生産者の世代交代が進んだらどうでしょうか。卸への付き合い方は変わるのではないでしょうか。
そういう意味で、一歩舵取りを間違えれば自爆する可能性もあることをやっている、と感じます。
そして、そういうところを走らないといけないほど、業界は危機感を持っているという空気を感じます。
みなさんはどうでしょうか?
今やらないと、始まらない
まだ政府の融資や補助金が追加投入されている今、最後のチャンスのように思います。持続化給付金に始まり、事業再構築補助金、一時支援金、ついで月次支援金が発表されました。
新型コロナウイルス感染症関連 (METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/
金額は会社規模によって受け取る感覚は様々でしょうが、支援が続いている事自体は安心材料に思います。
以前から全てがデジタルでしっかりデータ連携できていれば、企業でも個人でも、必要なところに必要なだけのサポートができたとは思いますが…反発がなぜこんなに大きいのか、私としては首を傾げるところです。
さておき、特にWebは投資対効果が良いですしリサーチが楽ですので、最初の一歩としては良いですね。
我田引水感があってごめんなさい。ただ、実店舗建てるのとネットで販売拠点となるHP作るのではコストが1桁いや2桁違いますし、取れるデータも遥かに多いです。
テスト商品を出すにしても、広告で集客するのはすぐですし、すでに蓄積されたさまざまなユーザーのデータもあります。
うちでも、じっくり腰を据えて新しいものを世に出したいというお客様から、とにかくネット上でこれを売れる拠点を作りたいという方まで、中小企業の方優先ですが、たくさんやっています。
こちらも熱意を持ってやっていますので、よろしければご相談ください。補助金周りのサポートも可能です。
Webinar最新回のご案内
第285回:生物の歴史から考える、これからの企業が生き残るために必要な姿勢と行動
今回は、今襲われている新型コロナとそれにまつわる様々な、政治的・社会的な災害に対して、どのように対応していいかのヒントとなる内容です。
今回の波が収まったとしても、過去にペストやスペイン風などがあったように、同様のストームが来ることは確実ですし、それ以外にも様々な天災やあるいは人災が起きることもあるでしょう。
そういった時に、どうやって生き残っていけばいいのか。
その一つのヒントが、過酷の環境でなんども絶滅しかかってきた生物の歴史であり、それをベースにした時に私たちが普段から行っておくべき行動があります。
今回は、そんな内容をお送りします。よろしければお聞き下さい。
配信はこちらから
YouTubeのみ動画です。バックグラウンド再生でどうぞ。
iTunes公式ディレクトリPodcast音声配信
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/zhong-shan-yang-pingno-non/id750899892
GooglePodcast
http://bit.ly/google-podcast-jp
Spotify
https://open.spotify.com/show/0yBHyUelJHFtby5uD06UxU?si=fL7RT_T9RPivEu7cAjhqFA
YouTube
https://youtu.be/0QUkwRVbYHs
ほか「中山陽平 podcast」などで検索ください。
音声メディアについて対談しました
先日、ポッドキャスト10年選手同士での対談をしまして、
内容は…
- なぜポッドキャストをはじめたのか、続けているのか
- 反響はあったのか、どうなのか?
- 気をつけなければいけない音声メディアの特性とは?
- クラブハウスはなぜああなったのか
- 音声はマーケティングの中でどう使っていくのか?
など、
ライターの方が、
とても読みやすいのでぜひご覧くださいませ。
- 今、音声メディアが面白い! ポッドキャスター2名が予想する音声メディアのこれから《前編》
https://wepress.web-magazine.jp/special/210426/ - 今、音声メディアが面白い! ポッドキャスター2名が予想する音声メディアのこれから《後編》
https://wepress.web-magazine. jp/special/20210427/
LINE@再開しました、ピックアップです
平日ほぼ日刊で、400文字に収まる範囲でニュースへの雑感をお送りしています。ぜひ。
登録はこちら → https://lin.ee/5NzoMnY
その中から最近のものをいくつか抜粋です。いいなと思ったら、ぜひ登録して頂きタイムリーにお受け取り下さい。過去のものも多分タイムラインから見られるのではと…。
【1】インスタなどの有料機能は日本で機能するか?
https://japan.cnet.com/article/35170061/
これと、後はSpotifyがPodcastのサブスクを始めるというニュースがありました。5月にアメリカからテストスタートが決まっています。
これをうけて個人がスキマ時間で稼ぐ方法が…という話が出てきていますが、日本ではその方向は期待しない法が良いと思います。
最も気楽であり安価で歴史もある有料メルマガでさえ、読んでいる人はかなりマイナー。最近はNOTEが若干収益につなげていますが、ごく一部です。副業と言える金額を稼いでいる人は一握り。
日本だと、派手なスパチャか、広告という見えない課金が引き続きマネタイズのメインでしょう。
そもそも課金が主体というより、課金しているという姿を見せたいという自己顕示が本当の目的だと考えたほうが良いです。マネタイズを目指すならその傾向を押さえた上で戦略練ったほうが良いです。
有料音声プログラムをやるなら、プレミア系で高額(月額5,000円とか1万円とか)にしてバックエンド系に回すほうが良いと思います。
【2】寝ている間にパワポ資料ができている 夜中に働いてくれるサービス
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2105/06/news077.html
海外にアウトソースしていると、この辺の便利さにたどり着きます。途中でコミュニケーションが必要ない作業に限られますが…。
ただ、人を探すのが難しい(真裏ではなくて北米西海岸でも16時間ズレているので、十分なのですが)ので、こういうラッピングしたサービスが広がると良いと思います。価格重視だと、まだまだベトナムやマレーシアなどかもしれません。
企業もフリーランスや海外人材活用(大体がBPO的な会社での対応ですね)できると、社内でやるべきことに集中できるので、おすすめです。私も、いくつかシンプルな作業やプログラム作りなどを依頼している先があります。デザインはセンスの方向性がかなり違うので、難しいですが…。
英語を話せる必要はないです、大体チャットでのやりとりになりますので、読み書きできれば可です。
さておき「Timewitch」というこのサービス現状はパワポだけなので、もっと広がると良いですね。
【3】注意:IT導入支援事業者に採択されるのは簡単、自社サービスを「認定」してもらうのも簡単です
IT導入補助金絡みのPRが増えてきたので注意喚起です。
よくプレスリリースなどで「 IT導入支援事業者に採択されました!経済産業省に認定されました」などというものがでます。ただこれ、全然とくべなものではないんです。私も支援事業者なのでわかりますが、手続書類や記載事項に不備がなければ、基本的にどこでも認定されます。
何か経済産業省のお墨付きをもらったとか、価値があるという判断をされたわけではないんです。
また、事業者として採択された後には、提供ツールを登録しなければなりません。コレが通ると、よくPRで「弊社の○○というツールが、経済産業省のIT導入補助金対象ツールに認定されました!」などとなるのですが、これも、規定を守っていれば基本的に通ります。
なので、そういうPRを見て「ここはすごいな」と思ってはいけないのです…
むしろ、針小棒大にPRを出すようなところは、近寄らないほうが良いかと思います。
何でしょうね、経済産業省認定という言葉が強いんですかね、あります…。お気をつけ下さい。
【4】GoogleマップでのNGパターンとは?コレを守ってない所に依頼は危険
「店舗がないとGoogleマイビジネスに登録できない!?非店舗の登録・運用方法 」
勘違いどころが集約された素晴らしいコンテンツです。フォーラムのエキスパートの方がやっているので信頼できます。
で、結構、本来はNGなことをやっている方少なくないです。
集客のために、ということなのでしょうが…。
例えば
「フリーでWeb制作、屋号が明確に表札や看板で表示されてない、またはその場所で接客していないのに、ビジネス登録している」
よくありますね。
Googleマップは「地図」ですので、行けてサービス提供される場所しか登録不可。
出張系やオンライン系は全部「非店舗系」。住所は掲載できずピン非表示、サービス地域だけの掲載です。
しかもマップでヒットさせたいがために、屋号を都合の良いものにしたりする、完全NGです。開業届に出したものしか使えません。
そういう所はローカルSEOに関するノウハウがないということですから、依頼しないことをおすすめします…。
書籍は最初の一歩にお勧めです
Amazonか大手書店で販売中です。
さて、この本は、企業のウェブ担当者・経営者などの方に伝えたい内容がメインです。
フリーランスでマーケターとしての腕を上げたい、SEOや広告のテクニックを学びたいという方向けの本ではありません。
Amazonだと中身が見られないので、そこだけ気にして頂けると、ミスマッチも少なくなるかなと思います。是非読まれた方はブログやAmazonなどでレビュー書いて頂ければ幸いです。
今後の配信コンテンツの方向性を決める上で、是非生の声を頂きたいです。
今すぐAmazonでご購入ください → http://amzn.asia/15AeH9k
終わりに
1週間空いてしまいました、反省です。GW前にやったつもりになっていました…。
さて、今日目にした記事で大事だなと思ったのはこれです。
Googleの「コロナ感染者予測」は信頼に足るのか 専門家がメカニズムを解説(1/2 ページ) – ITmedia NEWS
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2105/05/news013.html
都合の良いときにマスコミに使われ、何もなければ見向きもされない、Googleのコロナ感染者数予測です。
結果的には大外れだったわけですが、そもそも初めての事象で要因も分からないのに、参考数値以上の何でもないことは当然です。
なので、これを使って主張をするのはいかがなものかなわけですが、数字のインパクトが大きいのとGoogleという名前があるので、マスコミがたくさん使いましたね。
今回のコロナは、とにかく「言いっぱなし」「煽りっぱなし」なのが一番私としては良くない事象だと思っています。検証していない。
専門家やコメンテーターが自分たちの言ったことが合っていたのか、外れていたのか検証して、間違っていたならそれを認めるということをしていない。
Webという数字が大事な世界で生きている身としては、無責任だなと思うところです。
映像コンテンツはこういう「辻褄が合わない」「一貫性がない」ことが表沙汰になりづらいので、コロナに限らず情報を摂取する際はお気をつけください。特にYouTube系ですね。
では、また次回もメールしますね。